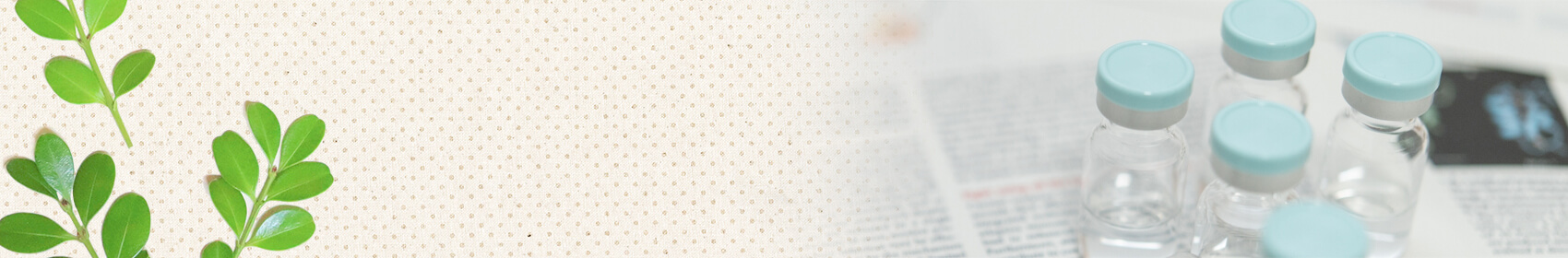
「最近、水が減るのが早い気がする」「何度もトイレに行っている」「食べているのに痩せてきた」愛猫にこのような様子が見られたら、それは糖尿病のサインかもしれません。
糖尿病は進行すると命に関わる怖い病気ですが、早期に発見して治療や生活管理を行うことで、症状を抑えながら長く健やかに暮らすことも可能です。特に猫では、肥満や膵炎といった生活習慣や基礎疾患が深く関わることが多く、日常生活での観察が何よりも重要になります。
今回の記事では、猫の糖尿病の原因・症状・検査・治療方法について詳しく解説し、さらに注目される新しい治療法(再生医療)までご紹介します。

猫の糖尿病は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌や作用が不十分になる病気です。その結果、血液中の糖がエネルギーとして利用できず、常に高血糖の状態が続きます。
典型的には、以下のような症状が現れます。
・たくさん水を飲んで尿の回数が増える(多飲多尿)
・食欲はあるのに痩せていく
・元気がない、疲れやすい、毛づやが悪くなる
猫の糖尿病は、人間のⅡ型糖尿病と似ており、肥満や運動不足、加齢、膵炎などが関係していると考えられています。インスリンは出ていても作用が弱まる「インスリン抵抗性」が背景にあり、結果的に血糖値が上がってしまうのです。
一方、犬では遺伝や加齢による発症が多く、肥満の影響は猫ほど大きくないという違いがあります。
猫の糖尿病は、次のような原因によって引き起こされます。
1.肥満
猫の糖尿病の最大のリスクです。脂肪が増えるとインスリンの効きが悪くなり、血糖が下がりにくくなります。肥満は生活習慣の影響が大きく、室内飼育で運動量が少ない猫や、自由採食(置き餌)をしている猫に多い傾向があります。
2.膵炎
インスリンを分泌する膵臓が炎症を起こすと、糖尿病を誘発します。膵炎が原因として疑われる場合、炎症を抑制するための新しいアプローチが治療のカギになります。
3.ホルモン異常やストレス
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)などのホルモン疾患や、強いストレスも発症要因になります。特に猫は環境変化に敏感で、引っ越しや新しい家族の加入などが大きな負担となることもあります。
猫の糖尿病を診断するには、以下の検査が必要になります。
・血液検査
血糖値を測定することで、その時点で糖が多いかどうかを判断します。ただし、猫は診察室でストレスを受けると血糖値が上がりやすいため、継続的な測定や「フルクトサミン」という長期的な平均血糖を反映する指標も確認します。
・尿検査
尿に糖やケトン体が出ていないかを調べます。ケトン体が出ている場合は重症度が高いサインです。
・画像検査や追加検査
膵炎や内分泌疾患を疑う場合は、超音波やホルモン検査を併用して鑑別します。
猫の糖尿病治療の基本はインスリン注射です。猫では作用時間の長いインスリンを1日1〜2回投与することが多く、種類や量はその子に合わせて調整します。
最近では、猫専用の経口薬(飲み薬)も登場しており、注射なしでも血糖コントロールが可能になってきています。
これらの治療法とあわせて、以下のケアも重要になります。
・食事療法
糖尿病用の療法食を使い、高タンパク・低炭水化物の栄養設計で血糖値を安定させます。給与量や回数を調整することも大切です。
・生活管理
適度な運動を取り入れることで肥満を防ぎ、血糖コントロールを助けることができます。また、猫は環境の変化に敏感な動物であるため、安心できる寝床や清潔で落ち着いたトイレ環境を整えるなど、ストレスの少ない暮らしを意識することが大切です。さらに、飼い主様が日常的に飲水量や尿の回数、体重を記録しておくと、病気の進行や治療効果を早期に把握する手がかりになります。
・定期的なモニタリング
治療を始めた後も、血糖値の測定や体調の観察を続けることが必要です。ポータブル血糖測定器を活用すると、よりきめ細かく管理できます。
膵炎が原因で糖尿病を発症している場合、従来の治療だけではコントロールが難しいことがあります。そこで注目されているのが間葉系幹細胞療法(MSC療法)です。
MSC療法は、膵臓の炎症を抑え、傷ついた組織の修復を助ける可能性があります。従来のインスリン治療や食事療法と組み合わせることで、インスリンの必要量を減らせる、血糖値をより安定させられるといった効果が期待されています。
まだ一般的な治療ではありませんが、糖尿病と膵炎が関わるケースで大きな希望となる選択肢です。
ご家庭で糖尿病の猫をケアする際には、以下のようなことに気を配りましょう。
・低血糖症状に注意
インスリンの量が多すぎると、逆に低血糖になることがあります。震えやふらつき、脱力などの症状は低血糖のサインですので、これらの症状がみられたらシロップなどを口に含ませた後、すぐに動物病院までお越しください。
・ストレス管理
愛猫の性格を考慮して、隠れられる場所や安心できる場所を用意し、できるだけストレスのない環境を整えましょう。
・定期的な健康チェック
体重や飲水量、尿量などを日頃からチェックし、変化があればすぐに獣医師に相談しましょう。また、病気の進行度や治療効果を確認するため、定期的に動物病院を受診しましょう。
猫の糖尿病は、肥満が最大のリスクであり、インスリン療法と食事療法による従来の治療が基本です。しかし、膵炎が関与している場合には、間葉系幹細胞療法といった新しい選択肢も視野に入れることで、治療の幅が広がってよりよいケアも期待できます。
「水をたくさん飲む」「トイレの回数が増えた」「痩せてきた」これらは猫からの大切なSOSです。
気になる変化に気づいたら、自己判断せず早めに動物病院へご相談ください。
◼️再生医療が何かより詳しく知りたい方へ
・「再生医療って何?」という疑問に答えます!ペットのための新しい治療法を、簡単にわかりやすくご紹介。大切な愛犬・愛猫にどう役立つのか、ぜひチェックしてください。
再生医療ってすごい!|ペットの治療をわかりやすく解説!・ペット医療の最前線を知りたい方におすすめ!再生医療がどうペットの未来を変えるのか、具体的な事例と共に最新の治療法を詳しく解説しています。
ペットの未来を変える再生医療とは?┃最新治療法を解説!
・再生医療で本当にペットの生活の質が良くなるのか?具体的な効果や改善例を通じて、愛犬・愛猫にとってどのような変化が期待できるのか詳しく解説しています。
再生医療って効果があるの? ペットのQOL(生活の質)の向上を判断します!
・再生医療に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。効果や安全性に関して不安を感じている飼い主様に向けて、わかりやすく疑問にお答えしています。
獣医が答える! 犬や猫の再生医療Q&A‐効果と安全性は?
◼️関連ページ
再生医療とは
再生療法(免疫療法)
愛知県碧南市の動物病院「へきなん動物病院」
℡:0566-41-1128