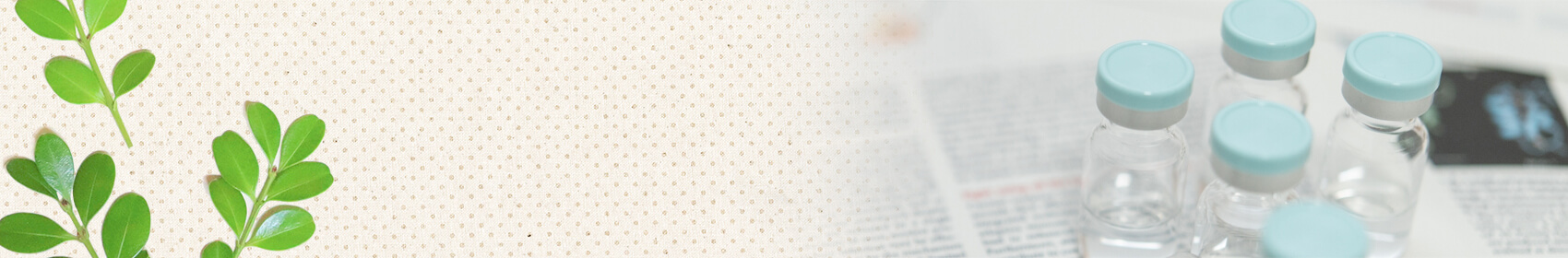
「うちの子、水をよく飲んでおしっこが多いような…」「ごはんは食べているのに、なんで痩せてきたんだろう?」愛犬のこうした何気ない変化は、見過ごされがちですが実は糖尿病のサインかもしれません。
放置してしまうと進行し、白内障や腎臓病などの合併症を招くリスクもあります。しかし、早めの受診と適切な血糖管理によって症状をコントロールし、生活の質(QOL)を維持することは十分可能です。
今回は犬の糖尿病について、その原因や症状、基本的な診断・治療方法をお伝えします。また、新たな治療法として再生医療(間葉系幹細胞療法)が注目されているため、その最新情報もあわせてご紹介します。

犬の糖尿病は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが不足することによって発症します。血糖値が下がらず、高血糖状態が続くのが特徴です。
典型的にみられる症状は以下の通りです。
・水をよく飲み、尿の回数が増える(多飲多尿)
・食欲はあるのに体重が減っていく
・以前よりも疲れやすく、元気がない
これらは初期症状としてよく見られますが、進行すると白内障や肝障害、感染症への抵抗力低下など、命に関わる合併症へとつながる危険があります。
糖尿病というと人の生活習慣病を思い浮かべるかもしれませんが、犬では少し事情が異なります。人の場合はインスリンが効きにくくなる「Ⅱ型糖尿病」が多いのに対し、犬ではインスリン自体の分泌量が減る「Ⅰ型糖尿病」に似た仕組みで起こることが多いのです。
さきほどもお伝えしたとおり、犬ではインスリンの絶対量が不足することで糖尿病になります。これは、膵臓のβ細胞(インスリンを分泌する細胞)が破壊されることでインスリンの量が不足し、血糖値を下げられなくなることが主な原因です。その背景には以下のような要因が関わっています。
1.遺伝的要因
ミニチュア・シュナウザーやテリア系など、一部の犬種で発症リスクが高いと報告されています。
2.加齢
中高齢(8歳以上)の犬で発症が増える傾向があります。
3.膵臓の炎症や感染
膵炎などにより膵臓がダメージを受けると、インスリンをつくるβ細胞も影響を受けます。
4.ホルモン疾患
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)や甲状腺機能低下症などが糖尿病を誘発する場合もあります。
また、メス犬では発情周期や黄体ホルモンの影響で糖尿病が悪化することがあるため、避妊手術も治療や予防の一環として検討されます。
糖尿病が疑われるとき、動物病院では以下の検査を行います。
・血液検査
血糖値を測定し、高血糖状態かどうかを確認します。ただし犬も診察室でストレスによって一時的に血糖値が上がるため、繰り返し測定や「フルクトサミン(過去2週間程度の血糖値の平均を反映する項目)」の測定で総合的に判断します。
・尿検査
尿に糖やケトン体(重度糖尿病で出る物質)が含まれていないかを調べます。
・他疾患の鑑別
甲状腺疾患やクッシング症候群など、似た症状を示す病気との鑑別も重要です。必要に応じて画像検査も併用します。
診断後も定期的な血糖測定が必要です。治療がうまくいっているか、低血糖を起こしていないかを確認するため、継続的なモニタリングが欠かせません。
犬の糖尿病は慢性疾患であり、基本的には生涯にわたる管理が必要になります。治療の柱は以下の通りです。
・インスリン療法
不足したインスリンを補うために、毎日のインスリン注射が基本となります。当院ではまず愛犬の状態を把握したうえで、インスリンの種類や量、投与方法、タイミングなどを見極めています。
・食事療法
食事は治療の大きな柱です。炭水化物を抑え、高タンパク質・高繊維質の療法食を与えることで、食後の急激な血糖上昇を防ぎます。毎日の給与量や時間を一定に保つことが大切です。
・運動と生活管理
適度な運動は血糖コントロールに有効です。ただし激しい運動は低血糖を招く恐れがあるため、散歩や軽い遊び程度にとどめます。規則正しい生活リズムを整え、過度なストレスを与えないことも重要です。
・定期的なモニタリング
治療開始後も定期的に血糖値を測定し、状態を見ながらインスリン量を調整します。最近では家庭で使える血糖測定器も普及しており、日常的な記録が治療効果の向上につながります。
従来の治療(インスリン・食事療法)に加え、新しい治療の選択肢として「間葉系幹細胞療法(MSC療法)」が注目されています。
この治療では、幹細胞が持つ抗炎症作用や組織修復機能を活用して、膵臓や免疫系の異常を改善しようとするものです。特に、膵炎など炎症を背景に糖尿病が発症した犬では、QOLの改善が期待される可能性があります。
ただし、
・犬での症例数はまだ限られており、効果は確立されていない
・あくまでも「従来治療の補助的手段」としての位置づけである
・導入には費用や通院頻度などの条件が伴う
などの理由から、実施にあたっては必ず獣医師との念入りな相談のうえでご判断ください。
犬の糖尿病は、長期にわたる管理やケアが欠かせません。日々の生活の中で、以下のようなことに注意するとよいでしょう。
・低血糖症状への対処
インスリンが過剰になると、逆に低血糖に陥ることがあります。震えやふらつき、脱力などの症状が出た場合は、シロップやブドウ糖を口に含ませ、すぐに動物病院を受診してください。
・ストレス管理と環境整備
ストレスは健康状態に悪影響を及ぼします。規則正しい生活を心がけ、リラックスできるような環境を整えてあげましょう。
・健康状態のこまめなチェック
日常の中で、体重・食欲・水を飲む量や尿の量などを観察し、小さな変化でも早めに獣医師へ相談しましょう。
犬の糖尿病は進行性の慢性疾患ですが、早めに気づいて治療を始めれば、元気に過ごすことも十分に可能です。
毎日のインスリン注射や食事の管理は大変な面もありますが、しっかりと血糖値をコントロールすることで、愛犬の体に負担をかけずに生活することができます。
また、最近では「間葉系幹細胞療法(MSC療法)」という、膵臓の炎症をやわらげる新しい治療法も少しずつ注目されはじめています。
「水をたくさん飲む」「おしっこの回数が多い」「体重が減ってきた」など、ちょっとした変化に気づいたときは、なるべく早めに動物病院を受診し、必要な検査を受けることが大切です。
◼️再生医療が何かより詳しく知りたい方へ
・「再生医療って何?」という疑問に答えます!ペットのための新しい治療法を、簡単にわかりやすくご紹介。大切な愛犬・愛猫にどう役立つのか、ぜひチェックしてください。
再生医療ってすごい!|ペットの治療をわかりやすく解説!
・ペット医療の最前線を知りたい方におすすめ!再生医療がどうペットの未来を変えるのか、具体的な事例と共に最新の治療法を詳しく解説しています。
ペットの未来を変える再生医療とは?┃最新治療法を解説!
・再生医療で本当にペットの生活の質が良くなるのか?具体的な効果や改善例を通じて、愛犬・愛猫にとってどのような変化が期待できるのか詳しく解説しています。
再生医療って効果があるの? ペットのQOL(生活の質)の向上を判断します!
・再生医療に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。効果や安全性に関して不安を感じている飼い主様に向けて、わかりやすく疑問にお答えしています。
獣医が答える! 犬や猫の再生医療Q&A‐効果と安全性は?
◼️関連ページ
再生医療とは
再生療法(免疫療法)
愛知県碧南市の動物病院「へきなん動物病院」
℡:0566-41-1128