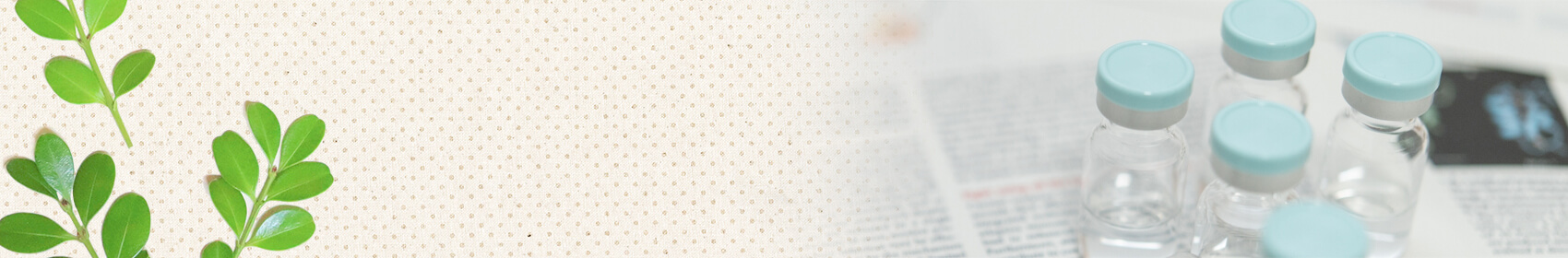
猫の平均寿命が延びるにつれて、シニア期特有の病気にかかる機会も増えてきました。その中でも特に多くの飼い主様を悩ませているのが、「慢性腎臓病(CKD)」です。
慢性腎臓病は進行性で完治が難しいという特徴がありますが、早期に発見し、適切に管理することで進行を抑え、QOL(生活の質)を維持することが可能です。これまででは治療法が限られていましたが、近年では再生医療などの新しい選択肢が登場し、希望の幅が広がりつつあります。
今回は、猫の慢性腎臓病についてわかりやすく解説しながら、最新の治療法についてもご紹介します。
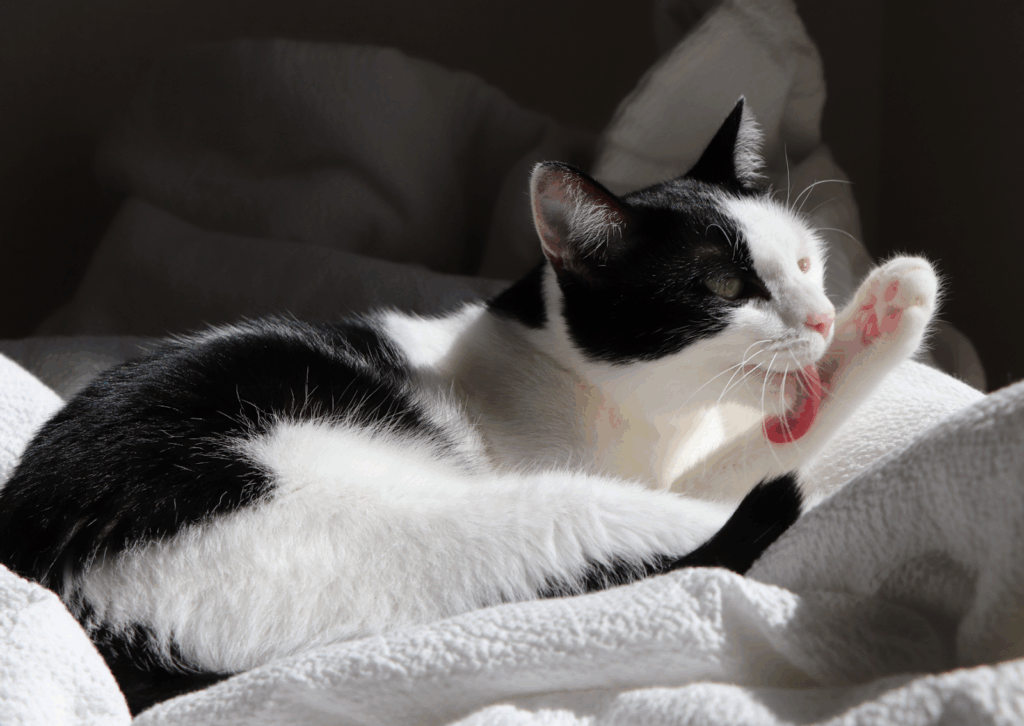
腎臓は、体内の老廃物を尿として排出したり、水分やミネラルのバランスを保ったりと、生命を維持するうえで欠かせない働きを担っています。猫が高齢になると、この腎機能が徐々に低下し、「慢性腎臓病」と診断されることが増えてきます。
高齢猫では特に多く見られる病気ですが、原因は加齢だけではありません。例えば、細菌やウイルスによる感染症、中毒、尿路結石や閉塞、遺伝的な体質、高血圧などの持病も腎臓にダメージを与え、慢性腎臓病を引き起こす要因となることがあります。
また、腎臓は「予備力が高い臓器(機能の一部が失われても残った部分で補うことができる)」であるため、機能が70%以上低下していても症状が現れないことが多く、気づいたときにはかなり進行しているケースも珍しくありません。
初期の段階では目立った症状はほとんどありませんが、少しずつ次のような変化が見られるようになります。
・水をたくさん飲む
・トイレの回数が増える
・食欲が落ちる
・体重が減る
さらに進行すると、次のようなより際立った症状がみられるようになります。
・嘔吐する
・口臭が強くなる
・被毛のツヤがなくなる
・元気がなくなる
しかし、これらのサインはご家庭ではなかなか気づきにくいので、シニア(7歳以上)の猫は年に1回以上健康診断を受け、血液検査で腎臓の数値をチェックすることをお勧めします。
具体的には、BUN(血液尿素窒素)、Cre(クレアチニン)、SDMAといった項目が腎機能の評価に役立ちます。あわせて、尿検査で尿比重や尿タンパクの有無を確認することも、早期発見につながります。
現時点での治療法は「対症療法」が中心で、腎機能の回復ではなく、進行を遅らせて生活の質を守ることが主な目的です。具体的には次のような選択肢が挙げられます。
・食事療法
腎臓病用の療法食を与え、リンやタンパク質の摂取量を調整します。
・水分補給の工夫
慢性腎臓病では脱水症状が起こる危険性があるので、水分摂取はとても大切です。ご家庭では、水飲み場を増やす、常に新鮮な水を用意する、ウェットフードを活用する、といった工夫がポイントになります。
・皮下輸液
脱水を防ぐため、輸液によって水分を補います。一般的には病院で処置しますが、状態によってはご自宅での実施も可能です。
・薬物療法
高血圧や貧血などの合併症に対して薬を使用します。
従来の治療法では限界がある中で、最近では新たな選択肢として「再生医療」が注目されています。特に猫の慢性腎臓病に対しては、間葉系幹細胞(MSC)療法が利用されます。
この治療法は、幹細胞がもつ抗炎症作用(炎症を鎮める作用)や組織修復促進効果(傷を治す効果)を活かして、慢性腎臓病のような進行性の病気による症状を和らげたり、QOLを改善させたりするものです。
実際にMSC療法を受けた猫の中には、腎機能(ろ過機能)の数値が改善したケースも報告されています。ただし、MSC療法は単独での効果を保証するものではなく、従来の治療法と組み合わせることで、より良い結果が期待される治療法です。
「間葉系幹細胞(MSC)療法」についてより詳しく知りたい方はこちらもご覧ください
愛猫が慢性腎臓病と診断されたら、日常生活では次のような工夫が役立ちます。
・ストレスの軽減
トイレや寝床は人通りが少ない場所に配置する、快適な温度・湿度を保つなどが重要です。
・生活リズムを整える
急激な環境変化によるストレスを防止しましょう。
・投薬や処置は手早く・やさしく
愛猫の負担を減らすため、処置は短時間で終えるとよいでしょう。
・こまめな体調チェック
体重や食欲、排泄の状態などを日常的に記録して、変化にすぐ気づけるようにしましょう。
猫の慢性腎臓病は残念ながら完治が難しい病気ですが、早期に発見し、適切な治療と日常管理を行うことで進行を抑え、快適な生活を維持できる可能性が高まります。
最近では、再生医療である間葉系幹細胞療法(MSC)という新しい選択肢も登場し、腎機能の改善が期待できるケースも報告されています。これまで治療に限界を感じていた飼い主様にとって、希望を持てる新たな道となるかもしれません。
当院でも、慢性腎臓病に関するご相談をいつでも受け付けています。最新の治療法を含めた選択肢をご提案できるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
<参考文献>
原田佳代子. 6.慢性腎臓病. In: 犬と猫の腎臓病診療ハンドブック. 上地正実 監修. 2021 : pp.104-123. 緑書房.
◼️再生医療が何かより詳しく知りたい方へ
・「再生医療って何?」という疑問に答えます!ペットのための新しい治療法を、簡単にわかりやすくご紹介。大切な愛犬・愛猫にどう役立つのか、ぜひチェックしてください。
再生医療ってすごい!|ペットの治療をわかりやすく解説!
・ペット医療の最前線を知りたい方におすすめ!再生医療がどうペットの未来を変えるのか、具体的な事例と共に最新の治療法を詳しく解説しています。
ペットの未来を変える再生医療とは?┃最新治療法を解説!
・再生医療で本当にペットの生活の質が良くなるのか?具体的な効果や改善例を通じて、愛犬・愛猫にとってどのような変化が期待できるのか詳しく解説しています。
再生医療って効果があるの? ペットのQOL(生活の質)の向上を判断します!
・再生医療に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。効果や安全性に関して不安を感じている飼い主様に向けて、わかりやすく疑問にお答えしています。
獣医が答える! 犬や猫の再生医療Q&A‐効果と安全性は?
◼️関連ページ
再生医療とは
再生療法(免疫療法)
愛知県碧南市の動物病院「へきなん動物病院」
℡:0566-41-1128